ビジネスモデル実用新案の進歩性に関する事例紹介

スペシャルコラム
Home > スペシャルコラム
ビジネスモデル実用新案の進歩性に関する事例紹介
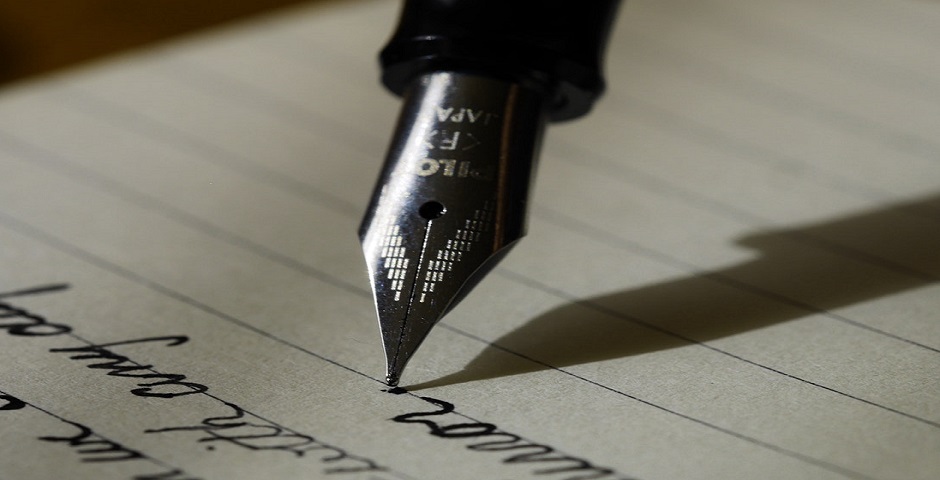
一、判決番号:智慧財産及商業法院110(2021)年度行専訴字第2号(民國 111(2022)年05 月 25 日)
二、争点:系争実用新案の請求項1において定義された「第1ユーザーが実店舗にて予約商品を購入した後、その実店舗の販売者端末デバイスを介して、サービス端末サーバーに保存された身分認証モジュールを情報接続して起動し、第1ユーザーの身分情報を正常に認証した後に、当該予約商品は未引換商品として、未引換商品リストに保存する」という技術的特徴が、組み合わせられた証拠との比較において進歩性を有するか否か?
三、係争実用新案補正後の請求項1の内容:
第1ユーザーが複数の予約商品を予約購入してギフトにするための、商品予約購入及びギフトプラットフォームシステムであって、以下の構成を含む。
▪第1ユーザーが所有する第1ユーザー端末デバイス:
この第1ユーザー端末デバイスにはユーザー端末アプリケーションがインストールされており、ユーザー端末アプリケーションはギフトモジュール、決済モジュールおよびログインモジュールを備える。ギフトモジュールは予約商品の贈答を可能にし、決済モジュールは取引情報の入力に用いられ、ログインモジュールはユーザーのログイン情報を入力するために用いられる。
▪サービス端末サーバー:
このサービス端末サーバーは、第1ユーザー端末デバイスと情報接続され、データベース、パスコード生成モジュール、引換証生成モジュール、決済サービスモジュールおよび身分認証モジュールを備える。データベースは商品リストおよび未引換商品リストを保存するためのもので、複数の予約商品が商品リストに列挙される。パスコード生成モジュールは少なくとも1つの商品引換パスコードを生成する。引換証生成モジュールは商品引換パスコードに基づき少なくとも1つの商品引換証を生成する。決済サービスモジュールは取引情報を保存するために用いられる。身分認証モジュールはユーザーの身分情報を認証するために用いられる。
▪実店舗における処理:
第1ユーザーが実店舗にて予約商品を購入後、当該店舗の販売者端末デバイスを通じてサービス端末サーバーに保存された身分認証モジュールを起動して情報接続し、第1ユーザーの身分情報が認証された後に、当該予約商品を未引換商品として登録し、未引換商品リストに保存する。これにより、第1ユーザー端末デバイスがギフトモジュールを実行した際、パスコード生成モジュールが起動し、当該未引換商品に基づき商品引換パスコードを生成する。
▪第2ユーザーが所有する第2ユーザー端末デバイス:
この第2ユーザー端末デバイスは、第1ユーザー端末デバイスから送信された商品引換パスコードを受信でき、その商品引換パスコードのガイドに従って引換証生成モジュールを起動して商品引換証を生成することができる。商品引換証は第2ユーザー端末デバイスの表示画面に表示される。
▪販売者端末デバイス:
この販売者端末デバイスは、サービス端末サーバーと情報接続し、商品引換証を読み取るために用いられる。商品引換証が読み取られると、商品受取完了メッセージを生成する。
四、係争実用新案が解決しようとする課題:
贈答者は、ユーザー端末コンピュータを介して、仮想プラットフォームサーバー上の仮想ショッピングインターフェースにおいて、実物商品を選択・購入することができる。贈答者がギフト受領者を選択すると、仮想プラットフォームサーバーはギフト受領者に対して商品受取識別コードを送信する。ギフト受領者は店舗内のマルチメディア機器にて商品受取識別コードを入力し、マルチメディア機器からプリントアウトされた商品受取伝票を取得し、それにより店舗内の実物商品を受け取ることができる。しかし、ギフト受領者は仮想プラットフォームサーバーのユーザーでなければならず、ギフトの受け取りに不便である。ギフト受領者はまずマルチメディア機器を操作して商品受取伝票を取得する必要があり、ギフトの引き換えも不便である。また、ギフト受領者が引換期限内にギフトを引き換えなかった場合、贈答者にとって無駄な浪費が発生する可能性がある。しかも、購入方法がオンラインショッピングに限定されているため、贈答者が店舗内で贈りたい商品を見つけた場合でも、携帯電話を所持していないと、その場で引換証をギフト受領者に送信することができない。したがって、オンラインとオフラインの購入方式を統合でき、店舗が自ら商品を追加できるギフトプラットフォームを提供すること、ギフトが期限内に受領されずに無駄になるリスクを軽減すること、ギフト受領者がギフトプラットフォームのユーザーでなくてもギフトを受け取れるようにすること、ギフトプラットフォーム(サービス側)が各店舗と個別に商品掲載交渉をしなくてもよい構成にすること、といった課題を解決することが求められている。
五、参加人(実用新案権者)の主張:
組み合わせられた証拠は係争実用新案の請求項1、2および4~7が進歩性を欠くことを証明するには不十分である
(一)証拠3は、ユーザーが実店舗で記名せずに迅速に商品(たとえば記名不要のゲームポイントカード。この商品は登録用シリアル番号のみ提供)を購入するという目的を達成するためのものである。当該ショップウェブサイトのサーバー端末商品が販売の記録も行う。たとえばサーバー端末が、当該商品が販売されたことを記録する際、対応するシリアル番号は「有効」である。つまり、購入者が対応するシリアル番号を用いた際、そのシリアル番号は「有効な」状態であるが、購入者が誰であるかは特に重視されない。引換者(最終的な利用者)は、「有効な」シリアル番号に基づいて使用するまたは商品を引き換えるにすぎない。一方、係争実用新案では、取引成立後から商品が引き換えられるまでの間、商品は常にユーザーに帰属し、かつ「オンラインとオフラインの予約購入」メカニズムを統合することで、当該技術分野における長年の課題を解決することができる。したがって、証拠3が解決しようとする課題は係争実用新案とは異なり、証拠3によって係争実用新案が進歩性を欠くことを証明することはできない。
(二)証拠3だけでは、係争実用新案が進歩性を欠くことを証明できず、また、係争実用新案が有する「ユーザーが実店舗にて予約商品を購入した後、すぐにその実店舗の販売者端末デバイス装置を介して、サービス端末サーバーに保存された身分認証モジュールを起動し、当該ユーザーの身分情報を認証した後に、当該予約商品は未引換商品として、未引換商品リストに保存する」という技術的手段は、証拠4にも開示されていない。証拠3および証拠4がいずれも商品予約・ギフトシステムの技術分野に属しており、相互に関連性があるとしても、その組み合わせでは、係争実用新案請求項1の進歩性欠如を証明することはできない。また、その他の請求項はすべて請求項1に従属しているため、各従属請求項についても進歩性を有すると評価されるべきである。
(三)係争実用新案の要点は、オンラインとオフラインの購買方式の統合にある。原告が提出した証拠1から証拠5の技術内容はいずれも、「カスタマイズには店員との確認が必要」などの記述があり、消費者は購入時点でその購入希望の商品がギフト用であるか否かを即決しなければならず、もしその場で決定できなければ、別途販売者との交渉が必要となり、この交渉をして初めて商品を譲渡できるようになることを示している。一方、係争実用新案は、オンラインとオフラインの機能の統合により、消費者と販売者が購買後に購入された一部の商品を第三者に贈答することを自ら選択できるようにし、消費行動に柔軟性を持たせるものであり、当該実用新案の出願目的は、引用証拠に示されるものとは明確に異なる。したがって、証拠1、2および証拠3から5はいずれも、単独でも、または組み合わせても、係争実用新案の各請求項が台湾専利法(特許法)第22条第2項(進歩性要件)および第26条第2項に違反する状況を証明することはできない。よって、係争実用新案は進歩性を有するものと認められるべきである。
六、法院(裁判所)の決定:
(一)証拠3の明細書段落[0017]および[0018]には、「ギフトおよび関連取引を促進するための方法、システムおよびソフトウェアを提供する…贈答者はショップカタログから1つまたは複数のギフトを選択し、支払情報(請求先住所を含む決済承認に必要な情報)を入力することで購入を行う…贈答者は、自身の連絡先情報(たとえばメールアドレスおよび/または住所)を入力することで、USNを有するギフト引換券をどのように、どこに送付するかを指定することができる」という技術内容が記載されており、取引情報を入力できる入力モジュールおよび予約商品を贈答できるギフトモジュールを備えたギフトプラットフォームシステムの技術内容が開示されている。
(二)証拠3の明細書段落[0019]には、「いずれかの送信方法が失敗した場合には、ギフト引換券または引換情報を再送信するためのリカバリ技術が用いられる。これには、既存または新たに作成された顧客アカウントおよびパスワードを利用し、ギフトを検索したり、カスタマーサービスセンターに電話したりすることが含まれる可能性がある」と記載されており、顧客アカウントおよびパスワードでログイン可能なログインモジュールを備えたギフトプラットフォームシステムの技術内容が開示されている。
(三)証拠3の明細書段落[0056]、[0157]および図15には、「贈答者106は、ブラウザ108を通じてオンラインショップのウェブサイト(またはオンラインショップ向けにギフト購入サービスを提供する第三者サイト)にアクセスする…図15に示されるクライアント端末には、モバイルデバイス1502、デスクトップパソコン1504、1506およびノートパソコン1508が含まれる」と記載されており、ユーザーが自身の端末デバイスを用いてアプリケーション経由でギフトプラットフォームシステムにアクセスするという技術内容が開示されている。
(四)証拠3の明細書段落[0017]および[0018]には、「ギフトおよび関連取引を促進するための方法、システムおよびソフトウェアを提供する…贈答者はショップカタログから1つまたは複数のギフトを選択し、支払情報(請求先住所を含む決済承認に必要な情報)を入力することで購入を行う」と記載されており、顧客の取引情報を保存する決済サービスモジュールを有するギフトプラットフォームシステムの技術内容が開示されている。
(五)証拠3の明細書段落[0019]には「いずれかの送信方法が失敗した場合には、ギフト引換券や引換情報を再送信するためのリカバリ技術が用いられる。これには、既存または新たに作成された顧客アカウントおよびパスワードを利用し、ギフトを検索したり、カスタマーサービスセンターに電話したりすることが含まれる可能性がある」と記載されており、顧客の身分情報を記録し、その認証を行う身分認証モジュールを備えるギフトプラットフォームシステムの技術内容が開示されている。
(六)拠3の明細書段落 [0056]および[0061]には、「オンラインショップは複数のデータベースに情報を保存しており、これには顧客データベース110、カタログデータベース112、購入データベース114、在庫データベース116が含まれる…ユーザーは、選択を完了した時点または任意のタイミングで、ブラウザ上の「カートを見る」ボタンやカートアイコンをクリックして、内容を確認・変更できる…さらに商品をカートに追加するには、「買い物を続ける」ボタン406を選択することで、ユーザーは再びカタログ画面に戻って商品を追加できる」と記載されており、ギフトプラットフォームシステムがユーザー端末デバイスと情報接続し、かつ商品リストおよび未引換商品リストを保存するデータベースを備えているギフトプラットフォームシステムの技術内容が開示されている。
(七)証拠3の明細書段落[0155]には、「オンラインおよび店舗でのギフトの購入および引換のいかなる組み合わせも想定され得る…店内でギフトを購入し、オンラインで引換する」と記載されており、さらに、同証拠の段落[0153]および[0155]には「ギフト引換券は、実店舗において、店員に確認するなどして特定の物品を識別し、店頭で受け取るか、あるいは自宅に配送される形で処理されることが可能である」と記載されており、証拠3には、ユーザーが実店舗にて予約商品を購入した後、実店舗の販売者端末デバイスを介してサービス端末サーバーと接続し、予約商品を「未引換商品」として登録されるが、そのプロセスには当然、ユーザーの身分認証が必要であり、その結果、予約商品が未引換商品リストに保存されることが開示されている。したがって、証拠3の段落[0153]および[0155]で開示された技術内容は、係争実用新案請求項1における「第1ユーザーが実店舗にて予約商品を購入した後、その実店舗の販売者端末デバイスを介して、サービス端末サーバーに保存された身分認証モジュールを情報接続して起動し、第1ユーザーの身分情報を認証した後に、当該予約商品は未引換商品として、未引換商品リストに保存する」という技術的特徴に対応している。
(八)証拠3の明細書段落[0018]には、「選択が完了すると、オンラインショップはギフト引換券を生成する。この引換券には、選択したギフトを引換するための意のセキュリティコード(USN)が含まれ…ギフト引換券は、電子メール、普通郵便またはSMSを通じてモバイルデバイスに送信できる」と記載されており、ギフト受領者が自身の所有するモバイルデバイスの表示画面上で、贈答者から送信されたギフト引換券を表示・確認できるという技術内容が開示されている。
(九)証拠3の明細書段落[0100]には、「ギフト引換券を取得した後(図3の枠300参照)、ギフト受領者は都合のよいタイミングで、当該ギフト引換券に記載されたリンクまたはその他の方法により案内され、指定されたウェブサイトにアクセスしてギフトを引き換えることができる…ユーザーは、引換サイト起動ページへのハイパーリンクを有する、オンラインショップのウェブページにある『ギフトを引き換える』ボタンを選び…」と記載されており、販売者端デバイスがサービス端末サーバーと情報接続し、ギフト受領者がギフト引換券を用いて商品を引き換えた時点で受取完了となる技術内容が開示されている。したがって、証拠3の段落[0018]および[0100]は、係争実用新案請求項1の「第2ユーザーが所有する第2ユーザー端末デバイスは…商品引換証は第2ユーザー端末デバイスの表示画面に表示される。販売者端デバイスがサービス端末サーバーと情報接続して当該商品引換証を読み取り、読み取りが完了すると、商品受取完了メッセージが生成される」という技術的特徴に対応している。
(十)上述の比較によれば、証拠3は、係争実用新案請求項1に類似した商品予約購入およびギフトプラットフォームシステムを開示しており、両者はいずれも、ユーザー(贈答者)が実店舗で商品を予約購入し、その後、サービス端末サーバーを介してオンライン上で該当予約商品の引換証(ギフト引換券)をギフト受領者に送信し、ギフト受領者がその引換証(ギフト引換券)を使って商品を引き換えるというものである。
(十一)証拠3と係争実用新案請求項1の違いは、係争実用新案請求項1の「パスコード生成モジュール、引換証生成モジュール、…パスコード生成モジュールは少なくとも1つの商品引換パスコードを生成する。商品引換証生成モジュールは商品引換パスコードに基づき少なくとも1つの商品引換証を生成…第1ユーザー端末デバイスがギフトモジュールを実行した際、パスコード生成モジュールが起動し、当該未引換商品に基づき商品引換パスコードを生成する…第1ユーザー端末デバイスから送信された商品引換パスコードを受信でき、その商品引換パスコードのガイドに従って引換証生成モジュールを起動して商品引換証を生成することができる」という技術的特徴を、証拠3は明確に開示していない点にある。
(一) 証拠4の技術内容を検討した結果、証拠4の要約には、「ギフトカードは、対応する店舗でギフトカード受領者によって引き換えられる」と記載されており、同証拠の明細書段落[0011]には、「サーバーは仮想ギフトカードに対して一意の識別コードを割り当て、ギフトカードの関連情報を識別するために使用し…サーバーはその後、一意の識別コードを受領者に送信する。一意の識別コードは仮想ギフトカード自体を含まない。一実施形態において、一意の識別コードはウェブページへのハイパーリンクであり…受領者はリンクをクリックしてギフトカードをリクエストする」と記載しており、サーバーがまず一意の識別コードを生成し、受領者はこの一意の識別コードをクリックすることで仮想ギフトカードを生成し、その後、この仮想ギフトカードを使用してギフトを引き換える。ここにおける、「一意の識別コード」は係争実用新案請求項1における「商品引換パスコード」に相当し、「仮想ギフトカード」は係争実用新案請求項1の「商品交換証」に相当する。証拠4の要約および明細書段落[0011]は、係争実用新案請求項1の「パスコード生成モジュール、引換証生成モジュール、…パスコード生成モジュールは少なくとも1つの商品引換パスコードを生成する。商品引換証生成モジュールは商品引換パスコードに基づき少なくとも1つの商品引換証を生成する。…第1ユーザー端末デバイスがギフトモジュールを実行した際、パスコード生成モジュールが起動し、当該未引換商品に基づき商品引換パスコードを生成する。…第1ユーザー端末デバイスから送信された商品引換パスコードを受信でき、その商品引換パスコードのガイドに従って商品引換証生成モジュールを起動して商品引換証を生成することができる。」という技術的特徴に対応する。
(二) 参加人は、111(2022)年3月28日の準備手続において、「係争実用新案の要点は、オンラインとオフラインの購買方式を統合する点にあり、原告が提出した証拠1〜5に含まれる先行技術は、いずれも店員とのやり取りを通じたカスタマイズ方式であり、消費者は購買時点で購入しようとする商品がギフト対象か否かを決定する必要があり、もしその場で決定しなかった場合は、改めて店側と協議して商品をギフト扱いにする必要がある。これに対し、係争実用新案は、オンラインとオフラインの機能を統合することにより、消費者と店舗の双方が、購入後に一部の商品を第三者へのギフトにするかどうかを自由に選択できる柔軟性を提供するものであり、この出願の目的は先行技術とは明確に異なる」と主張した。また、参加人は111(2022)年5月4日の口頭弁論において、「原告が提示した先行技術はいずれもカスタマイズ対応に限定されており、すなわち、消費者は購入時にその場で店舗にギフトサービスの実施を依頼しないとギフト注文ができない。これに対して、係争実用新案は、オンラインとオフラインのサービスを統合することで、消費者が商品購入後いつでも一部または全部の商品を第三者へのギフトにするかどうかを選択できるようにしており、店舗の協力を必要としない」と主張した。しかし、証拠3の明細書段落[0061]には、「ユーザーは選択が完了した後、または任意の時点で『カートを見る』ボタンを押して、内容を確認または変更することができる」と記載されており、同明細書段落 [0153]および図11には、「ギフト引換券は、実店舗の販売員に依頼してマークを付けるなどして…ギフト引換券は即座にプリントアウトされたり、メールやその他の手段によって贈答者に送信されたりする。…ギフト受領者は、図11のフォーム1100でギフトを変更し、図12のフォーム1200で配送方法を変更し、図13のフォーム1300でその他料金の支払うこが可能である」と記載されており、贈答者は商品購入後であっても、ギフトにする商品を変更することができ、さらに、ギフト受領者も商品引換証を受領した後にギフトの内容を変更することが可能であり、贈答者が未発送の商品を第三者に再度贈答することも当然可能であるという技術内容が開示されており、これは参加人が述べた係争実用新案の目的とも矛盾しない。
七、結論:
近年、ソフトウェアの助けにより多くのサービスプログラムやビジネスプログラムから新しいビジネスモデルが生まれており、多くの出願人が特許・実用新案によってビジネス方法やコンセプトを保護することを望んでいる。実際、審査官が新規性、進歩性について検索する際に、同じ先行技術を見つけることは容易ではなく、関連分野(たとえば、本案件は、商品の予約購入及びギフトシステムに関する)を探し、開示された先行案件の情報の一部を通じて、先行案件の既に開示された技術の一部の特徴から類推することが多い。審査官は、商業的な概念や方法ではなく、請求項で定義された「技術的特徴」のみを考慮するため、出願人は先行技術では係争特許・実用新案の目的や効果を達成できなかったと考えることがある。したがって、特許・実用新案出願の構想や明細書の作成段階においては、できるだけ当該ビジネスモデルに密接に関連する、必要かつ独自性のある技術的特徴を組み込むことが、審査や審判での有利な判断を得るために重要であると言える。